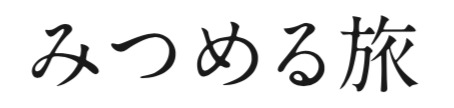2019/08/07 14:06

旅とは、自分の体と心を日常から離れた場所に置いてみること。いつもと違う風と光を浴び、いつも違う人と言葉に触れ、「非日常」で五感を満たしてみる。昨日までの連続を、一度ぷつりと断ち切ってみる。
感じることが変わると、考えることが変わる。考えることが変わると、やがて生きかたそのものも変化していく。旅に出る前の自分と、旅から戻った時の自分に、わずかでも変化があったなら、それはきっと”いい旅”だったと言えるはず。
長崎・五島列島を舞台に、そんな新しい旅の形を提案している「みつめる旅」。今回「みつめる旅」のスペシャルツアーとして、ベストセラー『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』の著者として知られる山口周さんと行く「みつめる旅humaity」を開催しました。
2019年9月に第1回が開催された「みつめる旅 humanity」の旅のレポート。今回、旅をしたのはこんな人です。
西村典哲さん▶︎▶︎▶︎ 1987年京都府生まれ。電通ビジネスデザインスクエア所属。「愛せる未来を、企業とつくる」という思想のもと、地方自治体、教育機関、企業における未来創造プロジェクトを多数実施。趣味は、カラオケ(出張先のスナック巡り)、BBQ(日本BBQ協会公式インストラクター)、建築巡り(京都に自邸を建築中)

「言語化できないこと」が最大の価値
こうして旅を振り返り、得られたことを言葉にしようとして気づきましたが、今回の旅は全体を通して「言語に依存しない時間」を過ごしていたと思います。「みつめる旅 humanity」に参加しているあいだは、とにかく五感を研ぎ澄ませていました。
柔らかな潮風の吹くビーチでダイアローグをしているあいだ、人工物がほとんどない海岸でひとり過ごしているあいだ、夜の海岸で焚火をしているあいだ、思い出してみると、東京にいる時とは比べものにならないくらい五感をフルに開いていました。

僕らには何事も言語化しようとする癖がついていますが、五島での経験はむしろ「言語化できないこと」こそが、大きな価値だったと思います。言語化することがなんだかもったいなくて、ためらいを覚えます。多面体の複雑なものを、単純化して二次元にしてしまうような感じですね。五感を通して身体に取り入れた豊かな情報をそのままに、自分の中に残しておきたくなる。そんな特別な時間でした。
「人間はどこへ向かうのか?」を考える旅
「みつめる旅 humanity」は、山口周さんを旅の案内人として「人間とは何か?」というテーマについて深く考え、語りあう3泊4日の旅です。
「人間とは何か?」って、壮大なテーマですよね。
僕なりにこのテーマについて考えをめぐらしていた時、フランスの画家、ポール・ゴーギャン(1897〜1898年)の名作「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」がふと頭に浮かんできました。僕はこの絵がすごく好きで。
普段から、自分が「どこから来たのか」「何者なのか」を学び、考えることはすごく大事だと感じています。結局、「どこへ行くのか」はその二つの問いに向き合わない限り見えてこない。仕事では、クライアント企業の方に対してビジネス提案をする場面が多いのですが、そのプロセスで企業として、何のために存在して、これからどの方向に向かっていくのか、という話をよくします。御社は、社会の中でどのような価値を提供するために生まれたのですか?と。

企業も、ミクロで見たら、結局は「人間」です。であるとするならば、「人間」はどこから来て、何者で、どこへ行くのか、を突き詰めて考えるしかありません。
その問いと向き合うのに、五島は適した場所だったと思います。150年前という人類の歴史の中でいえば「つい最近」まで続いていた、潜伏キリシタンをめぐる複雑な歴史に触れることで、人間がどういう生きものかを深くみつめられたと思います。しかも、ただ歴史に触れるだけではなくて、「ザザレ集落跡」(久賀島)の山道をトレッキングするなど、五感を通して追体験できるような内容だったことも大きかったですね。

「自分の行いは美しいのか?」という問い
個人的には、ちょうど2年前に息子が生まれ、「自分の行い」が社会にどのような影響を与えるかについて考えるタイミングであった点も、影響していたと思います。
ヨーゼフ・ボイス(1921〜1986年)というドイツの芸術家が唱えた、「社会彫刻」の概念があります。それは、一人ひとりが社会という作品を作っている、つまりあらゆる人がアーティストである、という考えかたであると僕自身は理解しています。社会を構成する一人ひとりが善い行い、美しい行いをすれば、世の中はあるべき方向に形づくられていく。だから、誰しもが美意識をもって日々を過ごそうという思想です。
これから生まれてくるわが子を育てる際に何を軸とするか、僕は妊娠中の妻と話しあいました。結果、「その子の行為が美しいかどうか」を基準にして対話していこうと決めました。息子が何かをした時に、「その行為は美しいのか?」と語りかけよう、と。
まだ2歳なので、その問いかけは思うようにはうまくいきませんが、息子に問いかけ続けていると、そのまま自分に跳ね返ってきます。じゃあ、自分の行いは、はたして美しいと言えるのか?と。これって、まさにヒューマニティーに関する問いですよね。

旅とは、本来「未知との遭遇」である
僕は普段広告代理店で働いていることもあり、日頃から上司と「人間をみつめることが自分たちの仕事だ」と話しています。結局、そこにしか答えはない、と。もちろん本を読んで「人間とは何か?」について考えることも大事ではあるものの、実際の行動を通じて自分の中に「哲学」を貯めていくしかないと思っています。
なかでも、とりわけ「人と接すること」は重視しています。反射で生きていない人、自分で考えて動いている人、普段関わらない領域の人に会うと、たくさんの発見があります。その意味で、「みつめる旅 humanity」を通じて出会った方々からは、他の参加者のみなさんからも、地元のみなさんからも予期せぬ刺激を絶えずいただきました。
旅の中で、地元のみなさんと交流する時間があったのですが、そのあと、とある人から「西村さん、イカ釣りに行きませんか?」と誘われたんです。で、人生で初めて釣りをすることになって(笑)。その時、予定調和でないことがなんだかとても嬉しくて、すごく「生きている感じ」がしたのを覚えています。

旅って、本来は「未知との遭遇」なんだと思います。
見知らぬ土地で触れる「未知のもの」「理解できないもの」「予期しないもの」が、旅の醍醐味ではないかと、今回の旅を通じて再確認しました。
予定調和でルーティーンの物事を進めるだけなら、究極的には人間でなくてもいいんです。予期せぬもの、アクシデントこそが人間を人間たらしめているのではないか、と。予定不調和と遭遇する経験を通して、新しい脳の回路が開いていくような快感がありました。そうした経験の蓄積が、人間としての「深み」になっていくのかもしれないと思います。

今後も「みつめる旅 humanity」に参加したみなさまのレポートも随時掲載してまいりますので、お楽しみに!
お知らせ▶︎▶︎▶︎「みつめる旅 humanity」は、初回はミレニアル世代から支持を集めるウェブメディア、Business Insider Japanさん主催の「五島列島リモートワーク実証実験」(後援:五島市、長崎県)内で開催された特別企画でしたが、今後は未来の社会をつくるビジネスパーソンを対象とした、紹介制のクローズド・ツアーとして運営していきます。
掲載写真について▶︎▶︎▶︎「みつめる旅」は、五島在住の写真家さんたちを中心となって五島の魅力を発信する「毎日が絶景PROJECT in五島列島」のメディアとして2017年にスタートしました。内面からの地方創生を目指して、1240キロ離れた五島と東京がたがいに大切な何かをGIVEしあえる持続可能な関係性を思索しながら運営しています。今回の「みつめる旅 humanity」の写真は、福江島在住の写真家・廣瀬健司さんが撮影しています。五島で生きる人だからこそ知っている「五島」を伝えるため、廣瀬さんは、ツアーの構成や旅程のプロデュース、現地のアテンドまで関わられています。