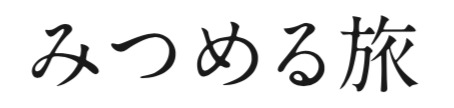2019/07/05 07:04

旅とは、自分の体と心を日常から離れた場所に置いてみること。いつもと違う風と光を浴び、いつも違う人と言葉に触れ、「非日常」で五感を満たしてみる。昨日までの連続を、一度ぷつりと断ち切ってみる。
感じることが変わると、考えることが変わる。考えることが変わると、やがて生きかたそのものも変化していく。旅に出る前の自分と、旅から戻った時の自分に、わずかでも変化があったなら、それはきっと”いい旅”だったと言えるはず。
長崎・五島列島を舞台に、そんな新しい旅の形を提案している「みつめる旅」。今回「みつめる旅」のスペシャルツアーとして、ベストセラー『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』の著者として知られる山口周さんと行く「みつめる旅humaity」を開催しました。
2019年9月に第1回が開催された「みつめる旅 humanity」の旅のレポート。今回、旅をしたのはこんな人です。
五島希里さん▶︎▶︎▶︎1984年東京生まれ。9歳の頃「どうしたら、生まれた環境を乗り越えて才能を発揮できる人が育つのだろう?」と思ったことをきっかけに、その解を探すべく、主に国際協力と人材育成の領域で活動。ユニセフやインドネシアの孤児院でのインターン、ESD研究、新規事業、コーチング、会社設立などの様々な体験を集約しつつ、現在は「一人ひとりの『挑戦のストーリー』を支える環境をつくる」をミッションとした会社を営む。

優秀なビジネスパーソンほど「内省の時間」を求めている
「みつめる旅 humanity」では、参加者同士が自由に語らうダイアローグの時間がたくさんあったことが、まずとても印象的でした。ビーチの前で潮風にあたりながら、夜空の下で焚き火を囲みながら、とりとめのないことから、生き方や価値観に関わるような深い話まで、何時間も一緒に語らっていました。
その様子から、ビジネスパーソンは、今こういう時間をとても求めているのだな、と強く感じました。普段、私自身が仕事でコーチングをしているので、なおさらそのニーズがすごくあることを再認識しましたね。
東京でも、こういう内省や対話を取り込んだ研修はありますが、社内の会議室などでやることも多いためか、「一個人として」というよりも、どうしても「会社のために」「組織のために」という部分が前に出てしまいがちです。でも「みつめる旅 humanity」では、会社の中の肩書を外して、たがいに利害関係のない者同士で、東京から1240キロも離れた五島の自然の中で語らうスタイルだったので、おのずと「ひとりの人間」に戻って内省と対話の時間を持てたのだと思います。
ひとりの人間として、何のため生きているのだろう、働いているのだろう、と深く考える時間。今回の旅のメンバーもまさにそうでしたが、組織の中でバリバリと仕事をし結果を残している優秀な人ほど、そういう時間を渇望している時代なんですね。

海辺でのチェックイン
一般的に研修では、最初によく「チェックイン」の時間をとります。
「チェックイン」とは、場を作るために参加者のみなさんの気持ちや状況を共有することです。「みつめる旅 humanity」でも、五島の幸をふんだんに使ったランチをいただいたあとに、ビーチでチェックインの時間がありました。
驚いたのは、そのチェックインでの自己開示の深さ、ですね。「息を吸って吐くように、今の心の中にあることを言葉にしてください」「誰からも評価を受けることのない安全な場所です」と事前に伝えられていましたが、それにしても参加者一人ひとりがあれほど安心して、自分自身のことを言葉にできる場は、他のいろいろな研修を見てきても稀有だと思います。

チェックインの間、耳に届くのは、風の音と鳥の声、あとは話している人の声だけ。そのせいか、一人ひとりの声がとても印象的に耳に残りました。これだけ集中して、人の声を聞くことは実は日常の中ではほとんどないかもしれません。
チェックイン以外の研修内容も、時間割を細かく入れ込みすぎず合間に合間に「何もしない時間」が適度にあったのが、とてもよかったですね。それが、決められたタイムラインに沿って物事をきちんとこなしていくことに慣れてきっている私たちビジネスパーソンにとっては新鮮でした。
身体で感じる「歴史」
2日目と3日目は、五島列島最大の島・福江島(ふくえじま)から離れて、久賀島(ひさかじま)と奈留島(なるしま)に行きました。
その中で、久賀島の森をトレッキングして「ザザレ集落」の跡地を見ました。険しい山道を開拓して、小さな田んぼや畑を作り暮らしていた痕跡が、1960年代に無人になってから今も残っています。

苦しい中で道を拓いてきた人の存在が最初にあり、そこから脈々と続いてきた先に「今」がある。当たり前のことかもしれませんが、険しい山道を歩いていると、そのことが身体でわかるというか、とても腹落ちするんですね。私自身はクリスチャンではありませんし、潜伏キリシタンのことは教科書でしか知らなかったけれど、心を打つ何かが確かにありました。
でも、考えてみれば、物事って、すべてそうですよね。最初に切り拓いてくれた人がいるから、「今」がある。その連なりに自然と感謝の念が湧いてきました。そして、「今」をもっと大事にしたいな、と思うようになりました。
未来よりも「今」をちゃんと生きたい
私たちは、よく「これからの世界を生きていくためのスキル」を身につけなくてはといった話をしますよね。私も職業柄「21世紀スキル」と呼ばれるものを中高生に教えることがあります。でも、五島滞在中に、むしろ「今をちゃんと生きる力」が実はとても大事なんじゃないかと考えるようになりました。
つまり、将来に起こりうる何かのために技術を身につけるという発想ではなく、今を生きるために自分が持ちうるものすべてを働かせる。スキルやコンピテンシーといったものをいったん脇に置いて、発揮しなくてはいけない「生きる力」があると思います。要は、その人の人間性ですね。

普段は、頭を動かしてから身体を動かしていたけれど、身体を動かすことの方が先に来る。そんな場面が、五島ではたくさんありました。身体を先に動かしていると、余計なことを考えなくなります。また「いい社会人であるべき」「優れたビジネスパーソンであるべき」といった評価を受けない空間であることも、そうした思考や発想の切り替えにプラスに働いていました。
「これから」を生きるためのスキルに限らず、五島に行く前は、未来のことばかり考えていたなあ、気づきました。次に何をしたいか? 次に何を作り出したいか? そういうことばかり考えながら前を向いて走り続けていました。自分がこれからやろうとしていることが、本当に自分にとって、社会にとって、そして周囲の人にとって幸せなことなのか?と、一度立ち止まって考えるようになりました。
考えたところで、すぐに答えは出ないし、わからない。でも、それでいいと思っています。「わからないもの」をわからないままにしておくことは、実は難しい。何らかの解釈をしたり、意味をつけたりして、「頭」で結論を出して、「次」に行った方がラク。だけど、それをしないで、わからないままにしておく余裕が自分の中で生まれましたね。

「東京的価値観」からの自由さ
現地では、地元の方々と関わる時間もありました。
五島列島って、東京から地理的に遠く離れた日本最西端の離島なので、やはり感覚が普通の地方都市とは明らかに違いました。私自身は日本中いろんな土地を訪れてきた方だと思いますが、五島はいい意味で「東京的価値観」から自由だと感じました。限られた滞在期間ではあったものの、東京に迎合することもなく、憧れることもなく、フラットに生きている印象がありました。地方都市に行くとよく、「(東京と比べて)自分たちは○○だから」という言いかたを耳にしますが、そういう表現は全然聞かなかったですね。
五島市は、最近U・Iターンが増えて、20代、30代の人を中心に年間で200人超(2018年度)が移住しているそうです。そういう方々と接する機会もありましたが、みなさん、何の力みもなく「ここの暮らしが気に入っている」と話していました。自分を幸せに見せようとか、逆に卑下しようとか、そういうところがない自然な感じが好きでしたね。
どことも比べず「ここがいい」「今がいい」と言えることが、純粋にすごいな、と。私はこれからも東京で仕事をして一生懸命に生きていると思いますが、「未来」よりも「今」を大事にしていきたいです。
東京に戻ればすぐに忙しい日常に戻ってしまいましたが、生きる姿勢について、五島で感じたことは今も自分の中に確かに残っていると思います。
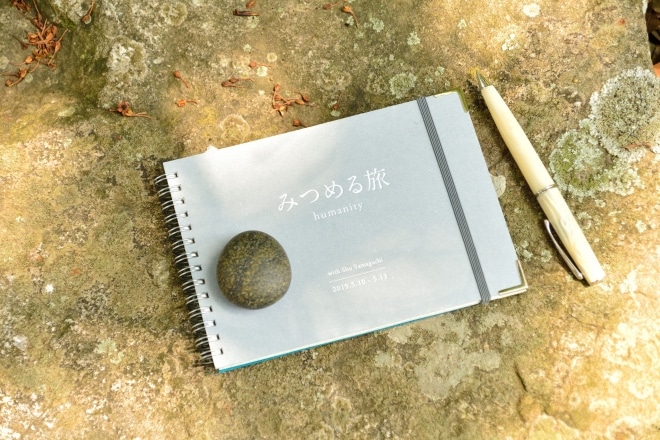
今後も「みつめる旅 humanity」に参加したみなさまのレポートも随時掲載してまいりますので、お楽しみに!
お知らせ▶︎▶︎▶︎「みつめる旅 humanity」は、初回はミレニアル世代から支持を集めるウェブメディア、Business Insider Japanさん主催の「五島列島リモートワーク実証実験」(後援:五島市、長崎県)内で開催された特別企画でしたが、今後は未来の社会をつくるビジネスパーソンを対象とした、紹介制のクローズド・ツアーとして運営していきます。

掲載写真について▶︎▶︎▶︎「みつめる旅」は、五島在住の写真家さんたちを中心となって五島の魅力を発信する「毎日が絶景PROJECT in五島列島」のメディアとして2017年にスタートしました。内面からの地方創生を目指して、1240キロ離れた五島と東京がたがいに大切な何かをGIVEしあえる持続可能な関係性を思索しながら運営しています。今回の「みつめる旅 humanity」の写真は、福江島在住の写真家・廣瀬健司さんが撮影しています。五島で生きる人だからこそ知っている「五島」を伝えるため、廣瀬さんは、ツアーの構成や旅程のプロデュース、現地のアテンドまで関わられています。